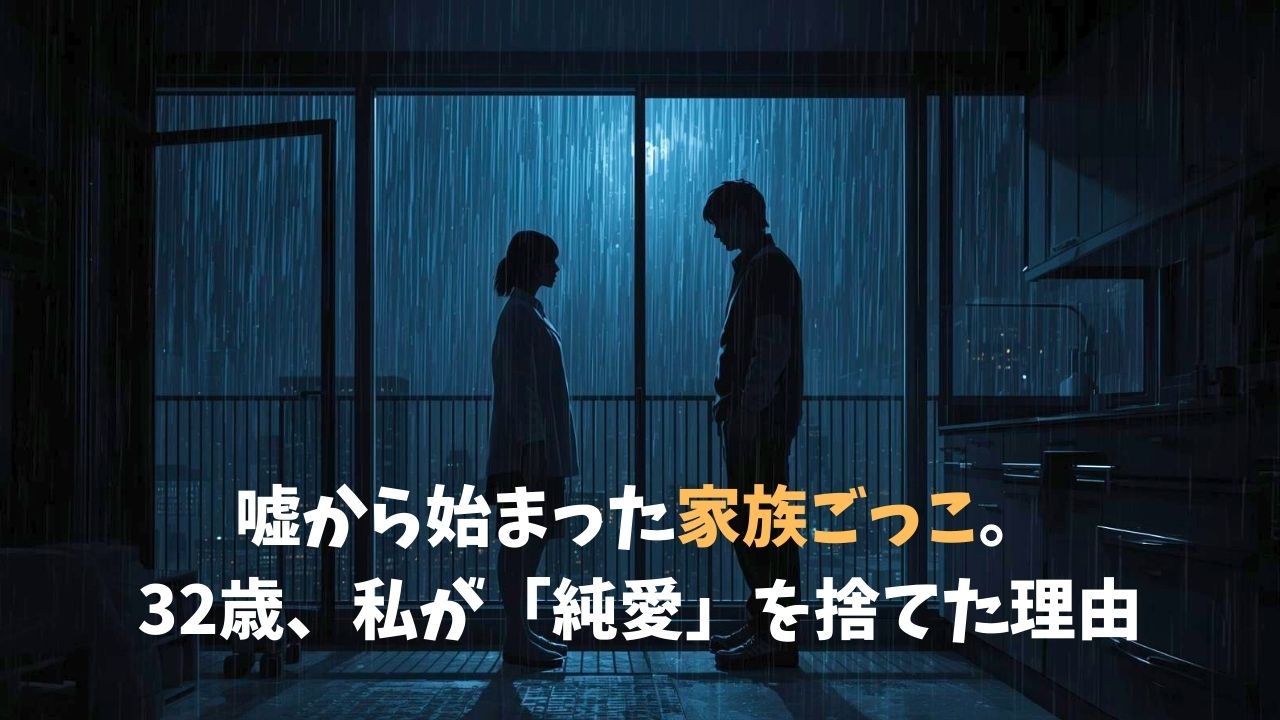「愛なんて、腹の足しにもならない」
ギャンブル狂の夫に捨てられた32歳の菜緒。過酷な毎日から抜け出すため、彼女が選んだのは「余裕のある男」和真を計画的に落とすことでした。しかし、始まった「家族ごっこ」の裏側には、彼が隠し持つ残酷な過去の罪が横たわっていた……。打算と贖罪が入り混じる、リアリティを追求した大人の再生ストーリー。
プロローグ:すり減る毎日と、一つの決意
32歳の菜緒(なお・仮名)は、3歳の娘・紬(つむぎ・仮名)を育てるシングルマザーだ。
「愛なんて、腹の足しにもならない」
それが、ギャンブルに溺れて蒸発した元夫が残した唯一の教訓だった。
昼は不動産会社の事務、夜は週に数回、飲食店でのアルバイト。鏡に映る自分の顔は、疲労と諦めで年々険しくなっていく。
ボロボロの賃貸アパートで、眠る娘の寝顔を見ながら、菜緒は冷めた頭で考えていた。
私が次に手に入れるべきは、胸が高鳴るような恋じゃない。私と子どもをこの泥沼から引き揚げてくれる「確かな生活」だ。
第1章:計算ずくの出会い
その男、和真(かずま)がパート先の不動産会社に現れたとき、私の本能は鋭く反応した。
「……いらっしゃいませ。本日はどのような物件をお探しでしょうか」
マニュアル通りの挨拶をしながら、私は彼の全身を瞬時にスキャンする。
仕立ての良いネイビーのスーツ、手入れの行き届いた革靴、そして左手の薬指には指輪なし。
落ち着いた物腰からは、人生の荒波を一度は越えてきたような静かな自信と、それでいてどこか「欠落」を感じさせる空気が漂っていた。
「職場に近い、静かな場所を。間取りは少し広めがいい」
低く響く彼の声を聞きながら、私は確信する。
この男は、私と子どもをこの泥沼から引き揚げてくれる「盾」になりうる存在だと。
私は、長年かけて磨き上げた「健気で、少しだけ影のある、一人の母親」という役を舞台に上げた。
わざとらしく自分の苦労を語るような下手な真似はしない。ただ、書類を渡すときの一瞬の指先の震えや、子どもの体調を気にする電話をあえて彼に聞こえるように受けるなど、小さな「フック」を丁寧に仕掛けていく。
「……お一人で育てていらっしゃるんですか?」
三度目の来店時、和真が不意にそう尋ねてきた。私は待っていましたと言わんばかりに、あえて数秒間の沈黙を置いた。
そして、少しだけ困ったような、けれど強気な微笑みを浮かべて答える。
「ええ。でも、紬がいてくれるから、全然平気なんです。仕事も楽しいですし」
その「強がり」こそが、和真のような余裕のある男性の庇護欲を正確に射抜くことを、私は知っていた。
「そんなに無理をなさらないで。……もしよければ、今度の休日に、お嬢さんも一緒に少し遠出をしませんか? 気分転換も必要でしょう」
和真の誘いに、私は心の中で快哉を叫んだ。
初回のドライブ当日。私はあえて派手な服を避け、清潔感のある淡い色のワンピースを選んだ。化粧は薄く、けれど肌のツヤだけは念入りに仕込む。
「紬ちゃん、初めまして。今日はよろしくね」
和真が娘に差し出したのは、高価な知育玩具だった。
「あ!おじちゃん、これ知ってる!」
無邪気に喜ぶ娘の背中を見ながら、私は和真に少しだけ申し訳なさそうな視線を送る。
「すみません、こんなに気を遣っていただいて……」
「いいんですよ。僕がそうしたかっただけですから」
和真の眼差しに、隠しきれない情愛が混ざるのを見逃さなかった。
獲物が罠にかかった感触。けれど同時に、私の胸の奥で小さな刺がチクリと刺さった。
和真が紬に向ける目は、単なる親切心にしてはあまりに熱く、執着に近い色を帯びていたからだ。
だが、その違和感を私は無視した。今は、この「完璧な父親」の役を演じてくれる男を、手放すわけにはいかなかった。
第2章:嘘と打算の綻び
和真と出会って三ヶ月が過ぎる頃には、私たちの週末は「家族」そのものの体裁を整えていた。
彼は、私がそれまで知っていたどの男とも違っていた。蒸発した元夫が「金」と「女」にしか興味がなかったのに対し、和真が執着したのは「紬」と「穏やかな家庭」だった。
「菜緒さん、紬ちゃんの幼稚園、ここがいいんじゃないかな。延長保育も充実しているし、何より教育方針がしっかりしている」
ある夜、和真が持ってきたパンフレットは、私一人の稼ぎでは縁がないような高級な私立幼稚園のものだった。
「……でも、和真さん。ここは月謝が、私には……」
「お金のことは心配しなくていい。僕が紬ちゃんの成長を支えたいんだ。いいだろう?」
彼の言葉は、救いだった。けれど同時に、底知れない恐怖でもあった。
彼はまだ、私に「結婚」の二文字を口にしていない。それなのに、まるでもう籍を入れた夫であるかのように、紬の将来に、私たちの生活に、深く、深く入り込んでくる。
ある週末、三人で郊外の大型モールへ出かけたときのことだ。
ふとした瞬間に紬が迷子になりかけ、和真が血相を変えて彼女を探し回った。
見つかったとき、彼は紬を強く抱きしめ、人目も憚らずに肩を震わせて泣いたのだ。
「よかった……本当によかった、もう、失いたくないんだ……」
その泣き方は、単なる迷子への心配を超えていた。まるで、過去に決定的な「喪失」を経験した人間が、そのトラウマに怯えているような、異様な執着。
私は、和真の背中をなだめながら、凍り付くような違和感を覚えた。
(この人は、私を見ているんじゃない。私を通して、別の何かを見ている……?)
その夜、彼が送り届けてくれたアパートの玄関で、私は初めて自分から彼を求めた。
彼の温もりに触れていれば、この胸のざわつきが消えると思ったから。打算で始めた関係だったはずなのに、いつの間にか私は、彼の優しさが「私個人」に向けられたものであってほしいと、切実に願うようになっていた。
しかし、抱き合っている最中、彼が私の耳元で囁いた言葉に、私は息が止まった。
「……いいママだね、菜緒さんは。君なら、今度は、きっと大丈夫だ」
「今度は」って、何?
私は彼の胸に顔を埋めたまま、何も聞けなかった。
和真が注いでくれる惜しみない愛情も、高価なプレゼントも、紬への献身も。そのすべてが、私の知らない「誰か」のための代償行為に過ぎないのではないか。
罪悪感と疑念が、泥のように私の心に溜まっていく。
私は和真に「いい母親」の顔を見せ続け、彼は私に「完璧な父親候補」を演じ続ける。
薄氷の上で踊るような、歪な幸福。 その氷が割れる日は、思ったよりもすぐそばまで来ていた。
第3章:暴かれた「救済者」の正体
その日は、和真のマンションで紬を寝かしつけた後、彼が急な仕事の電話でベランダへ席を外した。
その隙、 ふとした好奇心だったのか、あるいは彼が隠し持っている「影」の正体を突き止めたいという防衛本能だったのか。
私は、彼がいつも「ここは私室だから」と鍵をかけていた書斎のドアが、わずかに開いているのに気づいた。
吸い寄せられるように中へ足を踏み入れる。部屋は整然としていたが、デスクの引き出しの奥に、不自然に置かれた一冊の革装のフォトアルバムがあった。 手が震えるのを抑えながら、ページをめくる。
そこにいたのは、幸せそうに笑う若い女性と、三歳くらいの男の子。ページをめくるたび、日付が更新されていく。誕生日、遊園地、入園式。
そして、最後のページ。そこには、和真が大切に持っていたあの「知育玩具」と同じものを持って笑う男の子の姿と、その横に、今よりも少しだけ若い、でも今の彼とは決定的に違う「心から笑っている」和真がいた。
背後で、ドアが軋む音がした。
「……勝手に入るなと言ったはずだ」
氷点下の声。振り返ると、和真がドアの隙間に立っていた。
逆光で彼の顔は見えない。ただ、その輪郭から漏れ出る怒りと絶望の入り混じった気配に、私は射すくめられた。
「この人たちは、誰……?」
私の問いに、和真は力なく笑った。自嘲というより、心が壊れたような乾いた音だった。
「……僕が、守りきれなかった家族だ。仕事がすべてだと信じて、すぐ側にいた妻の異変に気づけなかった。ある日、いつものように遅く帰宅したら……部屋は真っ暗で、二人の時間は止まっていた。僕が買い与えたあのおもちゃを、息子は握りしめたままだったよ」
和真がゆっくりと私に近づく。
私は一歩、後ずさりした。
「君を選んだのは、君が『助けてほしい』という顔をしていたからだ。君と紬ちゃんを救い上げることで、僕はあの日救えなかった自分を、自分の過去を浄化したかった。……愛? 冗談だろう。僕が欲しかったのは、免罪符だ」
心臓が抉られるような衝撃だった。同時に、私の中の「黒いもの」が、鎌首をもたげる。
「……そう。なら、お互い様ね。私も、あんたを愛してなんてなかった。あんたのスペック、あんたがくれる生活、あんたが紬に払う月謝……それだけが目的だったわ。あんたがどれほど重い荷物を背負ってようが、私をこの生活から救ってくれるなら、それでよかったのよ!」
叫んでいた。涙は出なかった。あるのは、剥き出しになった醜いエゴのぶつかり合いだけだ。
私たちは、お互いを人間として見ていなかった。
和真は私を「過去の欠落を埋めるピース」として、私は和真を「都合の良い救済者」として消費していただけだった。
「……結局、私たちは自分のために相手を道具にしていただけね」
私は寝室で眠る紬を抱き上げ、乱暴に荷物をバッグに詰め込んだ。
この男の顔を見るだけで、自分の汚さが鏡合わせのように突きつけられて、息ができない。
しかし、玄関先で靴を履こうとした私の腕を、和真が強い力で掴んだ。
「……離して!」
「利用だっていい……理由なんて、何でもいいんだ……!」
和真の瞳は、真っ赤に充血していた。彼は私の腕を掴んだまま、崩れ落ちるように膝をついた。
「利用してくれ。君は生活を、紬ちゃんは未来を手に入れてくれ。……その代わり、僕は『父親』という役割にすがらせてほしい。一人でいれば、あの日から一歩も動けなくなる。君たちという重石がなければ、僕は自分を支えていられないんだ……」
プライドも、大人の余裕も、何一つ残っていない男の、無様な懇願。
私は彼を見下ろしながら、激しい嫌悪と、それ以上の共感を覚えていた。
私たちには、逃げ場がない。
愛という名の幻想を信じるには、私たちは汚れすぎていた。けれど、一人で生きていくには、あまりにも弱すぎた。
「……いいわ。続けましょう、この家族ごっこ」
私は、自分を掴む彼の冷たい手を、今度はゆっくりと握り返した。
「あんたは死ぬまで私に尽くして。私は死ぬまであんたを利用してあげる。……それが私たちの、唯一の正解よ」
それは、世間が呼ぶ「純愛」とは程遠い、歪で、汚い契約だった。
けれど菜緒は、その差し出された手を、今度は計算抜きで握り返した。
愛だけでお腹はいっぱいにならない。けれど、嘘と絶望から始まったこの「ごっこ」が、いつか本当の体温を持つかもしれない。
土砂降りの雨の中、菜緒は和真の胸に顔を埋めた。 ここから始まるのは、美しくない、けれど誰よりも切実な三人の「現実」だ。
第4章:歪んだ愛の、その先へ
和真のマンションに身を寄せてから、半年が過ぎた。
ダイニングテーブルを挟んで交わされる会話は、驚くほど事務的で、だからこそ一度も破綻することなく安定していた。
「和真さん、紬の習い事の振込、済ませておいたわよ」
「ああ、ありがとう。領収書はいつもの場所に置いておいてくれ」
あの雨の夜に交わした契約を、私たちは忠実に更新し続けている。
私は彼が提供する盤石な経済基盤に寄り添い、彼は私が提供する「父親という居場所」に救われている。
鏡に映る私の顔から、かつての険しさは消えた。高い美容液を使い、余裕のある服を纏い、私は理想的な「幸せな母親」を淀みなく演じている。
和真もまた、子どもに対して献身的な父親であり続けていた。彼が紬を抱き上げるとき、その瞳の奥に、時折別の誰かを追っているような虚無が過ることを、私はもう指摘しない。
私たちは、お互いの背負った「嘘」を暴かないという、暗黙のルールを共有する共犯者なのだ。
ただ、同じ時間を共に暮らしていると、時折、本当の家族なのではと錯覚することは増えていた。
エピローグ:嘘から芽生えた、本物の春
月日は流れ、紬のランドセルがすっかり背中に馴染んだ五度目の春を迎えた。
「ママ、パパ。見て、上手に描けた!」
小学校の図工の時間に描いたという絵を、紬が居間のテーブルに広げる。そこには、三人が手を繋いで笑っている絵が描かれていた。
かつて私が「家族ごっこ」と吐き捨てたあの光景が、子どもの目には、疑いようのない世界のすべてとして映っている。
「……上手だね、紬。一番いい場所に飾ろうか」
和真が紬の頭を撫でる。その手つきは、五年前のあの強迫的な献身とは、決定的に違っていた。
何かの代償としてではなく、目の前で生意気に笑い、自分を「パパ」と呼び続けるこの小さな存在そのものを、彼はようやく見始めている。
かつて失った家族への贖罪ではなく、今、横にいる紬の成長に、彼は生かされているようだった。
その夜、紬が眠りについた後、私たちは二人でバルコニーに立った。
「……菜緒。君は今、後悔しているか?」
夜風に吹かれながら、和真が不意に尋ねた。五年前と同じ問い。けれど、彼の声にあの頃の切迫感はない。
私は手元のグラスを揺らし、少し考えてから首を振った。
「後悔なんて、贅沢な感情よ。私はあの時、沈みかけていた船からあんたという島を見つけた。利用して、利用されて、そうやって生き延びてきただけ。……でもね、二人の足元に、いつの間にか地面ができていたことには驚いているわ」
「……そうだな。僕も同じだ」
和真が、私の肩を抱き寄せる。それは、最初の頃のような芝居がかった仕草ではなく、どこか心細さを分け合うような、穏やかな体温だった。
「愛してる」なんて、あの日以来、一度も口にしたことはない。
でも、打算と罪悪感の底から始まったこの関係は、五年という歳月を経て、私たちの骨身に深く馴染んでしまった。
嘘も、五年つき通せば、それはもう真実と見分けがつかなくなる。
そして、その冬。私たちの生活に、さらに半年後の変化が訪れた。
私の身体の中に、新しい命が宿り、そして無事に産声を上げたのだ。
「……パパ、見て! 赤ちゃん、私の指を握ったよ!」
病室のベッドの横で、紬が弾んだ声を出して身を乗り出す。お姉さんになった誇らしさと、新しい家族への純粋な好奇心で、彼女の瞳はキラキラと輝いている。
和真は、震える手で生まれたばかりの赤子を抱き上げていた。
「和真……」
私が声をかけると、彼はゆっくりとこちらを振り向いた。その目には、あの日絶望に沈んでいた男の影はもうなかった。
彼は、代わりを求めていた過去の亡霊から、ようやく解き放たれたのだ。
「菜緒、ありがとう。……紬、これから四人で、もっと賑やかになるな」
和真は、私の手を握り、もう片方の腕で紬を自分の方へ引き寄せた。
打算から始まった契約。嘘を塗り重ねた「家族ごっこ」。
けれど、地獄のような共依存の果てに、泥の中から蓮の花が咲くように、新しい命が生まれた。
子どもを囲んで笑い合う、この暖かな光。 これが、私たちが意地汚く生き延びた先で見つけた、唯一無二の真実だった。
理想の恋なんて、もういらない。必要なのは「明日を生きるためのパートナー」。 綺麗事だけでは生きていけない。でも、一歩踏み出せば、あなたの「現実」を丸ごと受け止めてくれる誰かがいます。打算から始まってもいい。それがいつか、二人だけの「真実」に変わるなら。30代、今から賢い大人の選択もありかもしれません。