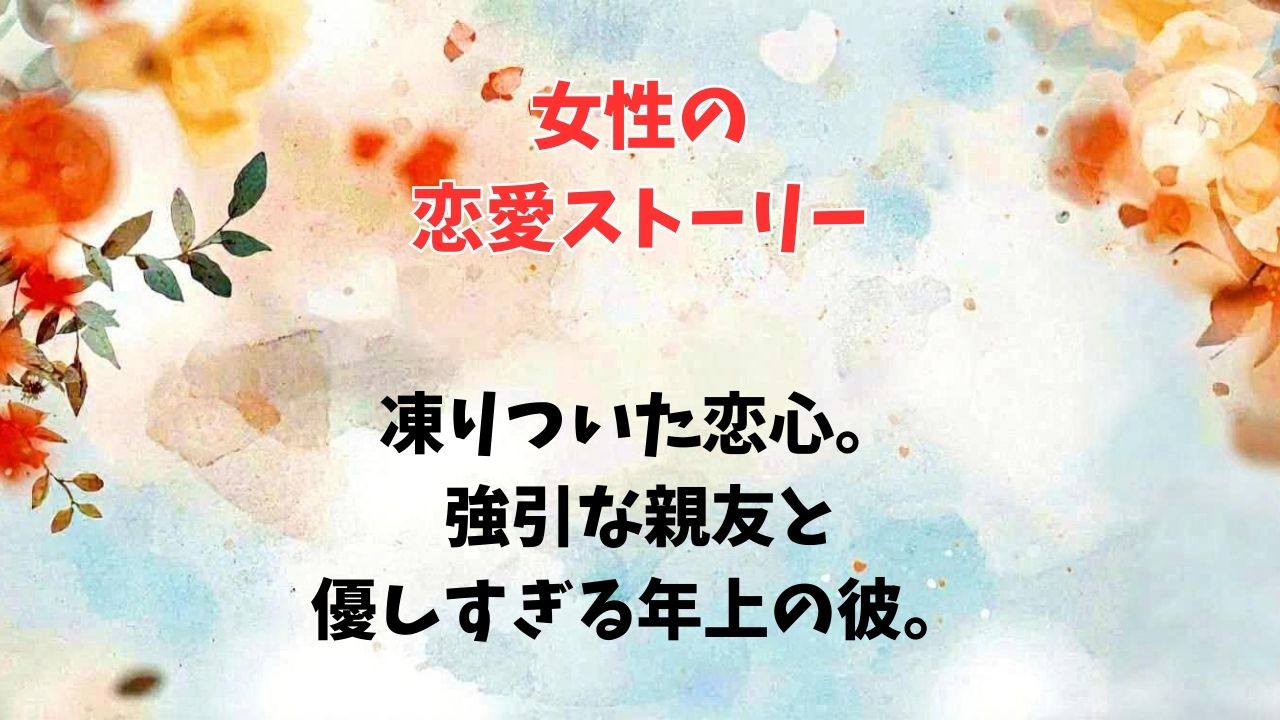これは、過去の恋に深く傷つき、一度は「恋をすること」を諦めた女性が、再生の一歩を踏み出すまでのストーリーです。
20代、信じていた人からの裏切り。冷え切った心で、自分には愛される資格がないと思い込んでいた彼女のスマホを、親友が強引に奪い取ったあの日。
止まっていた時計の針を動かしたのは、お節介な親友の愛と、年上の男性が持つ包み込むような優しさでした。恐怖心が信頼へと変わり、凍りついた心が溶けていく「再生」の軌跡を、ぜひご覧ください。
第1章:モノクロームの日常
「ねえ、いつまでそうやって殻に閉じこもってるつもり?」
カフェのテラス席。目の前に座る親友の陽菜が、呆れたような声を出す。私は手元の冷めたカフェラテをじっと見つめたまま、力なく微笑んだ。
私の名前は、佐藤あかり(仮名)。23歳。 一年前までの私は、もっと笑っていたはずだった。けれど、かつての恋人に投げつけられた言葉と、裏切りの記憶が、私の世界から色を奪ってしまった。
「お前みたいな重い女、他に誰も相手にしないよ」
「価値がないんだから、俺に感謝しろよ」
彼に尽くし、否定され続け、最後には他の女性のもとへ去られたあの日。私の心には分厚い氷が張った。男性の視線が怖くなり、優しくされることさえ「裏があるのではないか」と疑ってしまう。恋なんて、もう一生しなくていい。傷つかずに済むのなら、一人のほうがずっとマシだ。
「もういいの、陽菜。私は一人で平穏に生きていければ、それで」
「よくない! あんなクズ男のせいで、あかりの人生が台無しになるなんて許せない。……ちょっとスマホ貸して」
陽菜が、テーブルの上に置いてあった私のスマートフォンをひったくるように奪い取った。
「え、ちょっと、陽菜! 何するの?」 「いいから黙ってて。これが必要なのよ」
彼女は慣れた手つきで私の顔認証を突破(私がぼんやりと画面を見ていた隙だった)し、App Storeから一つのアプリをダウンロードし始めた。それは、今流行りのマッチングアプリだった。
「やめてよ! 怖いって言ってるでしょ」
「怖くない。私が横にいるうちに登録しちゃうんだから。名前は……『あかり』でいいわね。写真は、先週私が撮った奇跡の一枚があるからこれを使って……よし!」
私の制止も聞かず、陽菜の指は踊るように画面を叩く。わずか10分足らずで、私の「恋の窓口」は、私の意志とは無関係にこじ開けられてしまった。
「ほら、完成。嫌なら消せばいいけど、一週間だけやってみて。あかりを大切にしてくれる人は、世界にちゃんといるんだから」
返されたスマートフォンには、見慣れないアイコンが居座っていた。それは、凍りついた私の心に投げ込まれた、あまりにも強引な小さな火種だった。
第2章:画面越しの静かな足音
陽菜と別れた帰り道、バッグの中でスマートフォンが震えるたびに、私の心臓も嫌な音を立てた。
通知画面を見るのが怖い。また誰かに否定されるのではないか。見ず知らずの男性から、下心のある言葉を投げかけられるのではないか。 アパートに帰り、薄暗い部屋でようやくアプリを開いた。
「いいね」の通知がいくつか届いている。どれも若くて華やかな男性ばかりで、私は気圧されて画面を閉じようとした。その時、ふと一つのプロフィールが目に留まった。
「誠、34歳」
写真は、木漏れ日の中で穏やかに笑う男性のものだった。派手さはないけれど、アイロンの効いたシャツを着たその姿からは、落ち着いた大人の品性が感じられた。自己紹介文を読んでみる。
『仕事と家の往復ばかりですが、休日はゆっくり料理を作ったり、古い映画を観たりしています。派手な出会いは求めていません。お互いの歩幅を大切にできる方と、少しずつお話しできれば嬉しいです』
「歩幅を、大切に……」
その言葉が、ささくれ立った私の心に優しく触れた。過去の恋人は、いつも自分のペースを私に強要し、私が遅れることを許さなかった。 私は、震える指で「ありがとう」を返した。
数分後、彼からメッセージが届いた。
『マッチングありがとうございます、あかりさん。アイコンの写真、とても優しい表情をされていますね。今の時間は、お仕事帰りでしょうか? お疲れ様です』
それは、驚くほど普通で、驚くほど丁寧な言葉だった。
第3章:溶け始める氷
誠さんとのやり取りは、それから毎日続いた。
彼は決して急かさなかった。私が返信を一日忘れてしまっても、翌朝には
「おはようございます。今日も冷えますね」
と、何事もなかったかのように穏やかなメッセージをくれる。
少しずつ、私は自分のことを話し始めた。といっても、過去のトラウマを直接話す勇気はまだない。今日食べた美味しいパンのこと、会社で少し嬉しかったこと。そんな他愛もない話に、彼はいつも
「それは良かったですね」
「そのパン、僕も食べてみたいです」
と、温かい相槌を打ってくれた。
ある夜、私は思い切って彼に尋ねてみた。
「誠さんは、どうして私と話を続けてくれるんですか? もっと楽しい女の子はたくさんいると思うのに」
誠さんからの返信は、少し時間が経ってから届いた。
『あかりさんは、とても繊細に言葉を選んでお話ししてくれますよね。僕は、その誠実さが好きです。年齢や外見よりも、心の温度が合う人と出会いたかった。今の僕には、あかりさんの言葉が一番心地いいんです』
「心の、温度……」
画面を見つめながら、不覚にも涙がこぼれた。私は価値のない人間じゃない。私の言葉を待ってくれている人がいる。陽菜に無理やりこじ開けられた扉の先には、思っていたような怪物ではなく、暗闇を照らす小さな灯台のような人が立っていた。
やり取りを始めて一ヶ月。私たちは、初めて会う約束をした。
第4章:雨上がりの待ち合わせ
待ち合わせの日は、皮肉にも朝から雨だった。 鏡の前で何度も服装をチェックする。派手すぎず、でも失礼のないように。過去の彼に「似合わない」と言われて捨てたはずの、淡いベージュのスカートを、私は数日前に買い直していた。
約束の場所は、静かなホテルのラウンジ。
「あかりさんですか?」
声をかけられて顔を上げると、そこには写真よりも少し目尻に優しそうなシワを寄せた、誠さんが立っていた。
「はじめまして、誠です。雨の中、来てくれてありがとう。足元、濡れませんでしたか?」
彼の声は低く、落ち着いていた。緊張で固まっていた私の肩から、すっと力が抜けていく。 ラウンジで紅茶を飲みながら、私たちは話をした。画面越しではなく、直接交わす言葉の温度。彼は私の目を見て、私の話が終わるのを待ってから、ゆっくりと自分の話をしてくれた。
「実は私、男性と二人で会うのが、少し怖かったんです」
気づけば、私は隠していたはずの本音を漏らしていた。
「過去に、あまり良くない経験があって……自分が女性としてダメなんじゃないかって、ずっと思っていました」
誠さんは、カップを置くと、テーブルを挟んで私の目を真っ直ぐに見つめた。
「あかりさん。あなたは、何もダメなんかじゃない。その傷は、あなたがそれだけ一生懸命に誰かを愛そうとした証拠ですよ。これからは、自分を責めるためにその記憶を使わないでください」
彼の言葉には、年上の男性ならではの、重みと包容力があった。
「……頑張ったんですね、今日まで」
その一言で、私の中に残っていた最後の一片の氷が、音を立てて溶けていった。ラウンジを出る頃には雨は上がり、雲の隙間から柔らかな光が差し込んでいた。
第5章:愛されるということ
それからの私たちは、一歩ずつ、丁寧に距離を縮めていった。
誠さんはいつも私の体調や心の動きを最優先してくれた。人混みが怖くないか、歩くスピードは速くないか。彼は、私の「歩幅」に合わせることを、当たり前のようにしてくれた。
初めて手を繋いだとき、私は反射的に身を強張らせてしまった。けれど彼は、その手を離すのではなく、ただ優しく包み込んで
「大丈夫だよ、ゆっくり行こう」
と微笑んでくれた。
愛されるということは、誰かの言いなりになることではない。 お互いを尊重し、弱さをさらけ出し、それを守り合うこと。
二回目のデートの帰り道、彼は私を家まで送り届けてくれた。
「あかりさんに出会えて、僕の日常も色づき始めました。ありがとう」
別れ際、彼は私の頭を優しく撫でた。その手のひらの熱が、過去の冷たい記憶を上書きしていく。
季節が深まり、二人の間に確かな絆が育まれた頃。私は誠さんの家で、穏やかな夜を過ごしていた。 彼の手が優しく私の頬に触れたとき、過去の記憶が一瞬だけ脳裏をよぎった。けれど、目の前にいる誠さんの瞳はどこまでも温かく、以前のような恐怖心はもう、そこにはなかった。
「あかり、僕を信じてくれてありがとう」
その言葉とともに、重なり合った唇は、過去の冷たい記憶を上書きするほどに熱かった。 初めて結ばれたその夜、誠さんは私の震えが止まるまで、何度も何度も優しい言葉をかけ続けてくれた。かつての暴力的な一方通行の関係とは違う。それは、お互いの鼓動を確かめ合い、慈しみ合う、とても静かで神聖な時間だった。
彼に身を委ねる中で、私は自分の体がいかに強張っていたかを知り、同時に、誰かに愛おしまれることの幸福感を知った。
「もう、怖くないよ」
彼の胸の中でそう呟いたとき、私の心の中にあった分厚い氷の壁は、完全に消えてなくなっていた。
陽菜に報告すると、彼女は自分のことのように泣いて喜んでくれた。
「ほらね、言ったでしょ? あかりは愛されるべき人なんだってば」
スマートフォンの画面を奪い取ったあの日、陽菜が無理やり踏ませたアクセルが、私をこんなに穏やかな場所へ連れてきてくれたのだ。
エピローグ:再生の軌跡。新しい私へ
陽菜に報告すると、彼女は自分のことのように泣いて喜んでくれた。
「ほらね、言ったでしょ? あかりは愛されるべき人なんだってば」
今、私のスマートフォンのアルバムには、誠さんと行った場所の、色鮮やかな写真がたくさん並んでいる。 モノクロームだった日常は、もうどこにもない。
あの日、親友にスマホを奪われ、半ば強引に始まったマッチングアプリという名の「再生」。 過去の傷跡が完全に消えたわけではない。今でも時々、不安が顔を出す夜もある。けれど、そんな時は誠さんに電話をする。
「どうしたの? 眠れない?」 受話器越しに聞こえる、穏やかな年上の彼の声。それだけで、私の世界は再び安心感で満たされる。
恋愛は、傷つく可能性を孕んでいる。けれど、その痛みを恐れて立ち止まってしまうには、この世界はあまりにも美しい出会いに溢れている。
あの日、強引に背中を押してくれた陽菜に。 そして、臆病な私の歩幅に合わせて歩いてくれる誠さんに、心からの感謝を。
私の物語は、まだ始まったばかりだ。 壊れた心を抱えたまま踏み出した一歩は、今、確かな幸せへと続く軌跡となって、未来へ伸びている。 凍りついた恋心が溶けたあとには、今までよりもずっと温かく、優しい春が待っていた。