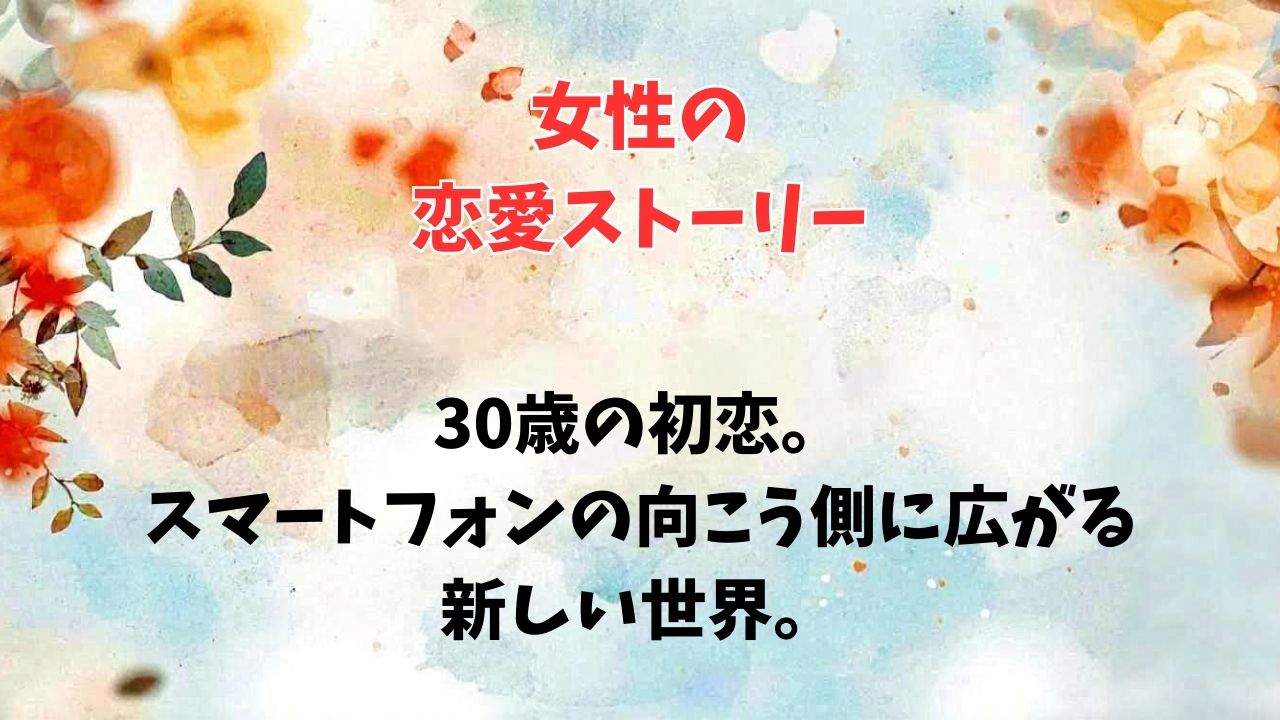これは、恋愛という未知の扉を前に立ちすくんでいた一人の女性が、勇気を出して自分の人生を動かし始めるストーリー。
30歳、恋愛経験なし。「自分には何かが欠けているのではないか」という不安を抱えながら生きてきた彼女が、マッチングアプリという現代のツールを通じて、どのように「知らなかった自分」に出会い、新しい自分を見つけていったのか。
切実で、けれど温かい「自分再生」の軌跡を、ぜひ最後まで見届けてください。
第1章:止まったままの時計
「美咲、今度の土曜日、空いてる? 久しぶりにみんなで集まらない?」
大学時代の友人、理恵からのLINEに、私はスマートフォンの画面を伏せた。既読をつけるのを躊躇ってしまうのは、集まれば必ずと言っていいほど「最近どうなの?」という話題になるからだ。
私の名前は沢村美咲(仮名)、30歳。都内の事務職として働き始めてから8年が過ぎた。仕事はそつなくこなし、人間関係も悪くない。けれど、私の人生の年表には、決定的な空白がある。
「恋愛経験、なし」
それが私の抱える、静かな、けれど重い秘密だった。 二十代の頃は「まだ大丈夫」と自分に言い聞かせてきた。仕事が忙しかったし、趣味の読書やプラネタリウム巡りだけで毎日は満たされていた。けれど、三十の大台に乗った瞬間、まるで世界の色が変わったように感じた。結婚報告の年賀状、SNSに流れてくる子どもの写真。同世代の友人たちが次々と「人生の次のステージ」へ進んでいく中で、私だけが、電池の切れた時計のようにその場に立ち尽くしていた。
「私だって、変わりたい……」
そんな思いが胸の奥で渦を巻いていた。でも、どうすればいいのか分からなかった。合コンに行く勇気も、誰かに紹介を頼む度胸もない。自分に自信が持てないまま、時間だけが残酷に過ぎていく。
そんな時、テレビや雑誌で目にする「マッチングアプリ」の存在が、少しずつ私の中で大きくなっていった。かつての「出会い系」とは違う、クリーンで身近なツール。勇気を出してアプリの公式サイトを開いてみたものの、そこには眩しいほどに輝く男女の写真が並んでいて、私はすぐにブラウザを閉じた。
「私みたいな魅力のない人間が、あんなキラキラした世界に行っていいはずがない」
そう決めつけて、またいつもの代わり映えのしない日常に戻る。けれど、その日の帰り道、夜空にポツンと光る一番星を見上げた時、なぜか涙がこぼれそうになった。このままじゃいけない。明日も、明後日も、一人で星を見上げるだけの人生でいいの?
私は駅のホームで、震える指先を動かした。アプリのダウンロードボタンを押した時の、あの心臓の鼓動を、私は一生忘れないだろう。
第2章:画面越しの迷宮
アプリをインストールしたからといって、すぐに世界が変わるわけではなかった。むしろ、本当の試練はそこから始まった。
まずはプロフィールの作成だ。ニックネーム、年齢、居住地……順調に入力していく私の指が、ある項目で止まった。
「マッチングアプリを始めたきっかけ」 「恋愛に対する考え方」
正直に「恋愛経験がない」と書くべきか、それとも「仕事が忙しかったから」と濁すべきか。画面を前にして一時間も悩んだ。嘘はつきたくないけれど、三十路で経験がないなんて引かれるに決まっている。結局、私は当たり障りのない「新しい出会いが欲しくて」という言葉を選んだ。
次に待ち構えていたのは、写真の壁だ。自撮りなんてしたことがないし、友人と撮った写真はどれも数年前のものばかり。クローゼットの中から一番清潔感のある白いブラウスを選び、スマートフォンのタイマー機能を使って、慣れない笑顔で自撮りを繰り返した。百枚近く撮り直して、ようやく「まあ、これなら……」と思える一枚をアップロードした。
設定が終わると、驚くほどの速さで「いいね」という通知が届き始めた。
「わっ……!」
スマホが震えるたびに、私の心臓も跳ねた。見ず知らずの男性たちが、私の写真を見て、興味を持ってくれている。それは初めての体験で、気恥ずかしさと、少しの期待が入り混じった不思議な感覚だった。
しかし、メッセージのやり取りは想像以上に難しかった。
「はじめまして!よろしくお願いします」
と送っても、そこから会話が続かない。
「お仕事は何をされてるんですか?」
「事務職です」
「そうなんですね。大変ですか?」
「いえ、それなりに……」
そんな味気ないやり取りを繰り返すうちに、私は次第に疲れを感じ始めていた。何が正解なのか分からない。相手の顔が見えない分、言葉の裏側を読みすぎてしまうのだ。既読がつかないだけで一晩中落ち込み、返信が来れば「なんて返そう」と一時間悩む。
「やっぱり、私には向いてないのかな」
一ヶ月が過ぎた頃、私の画面には誰とも続かないチャットの履歴だけが並んでいた。スマートフォンの画面に映る自分の顔が、ひどく疲れて見えた。
そんな時、ふと目に留まったプロフィールがあった。
田中健太(仮名)、30歳。建築関係の仕事。
写真は、どこかの公園で少し照れくさそうに笑っているもの。自己紹介文には、こう書かれていた。
『仕事ばかりの毎日ですが、たまの休みにはプラネタリウムに行って、ぼんやり空を眺めるのが好きです。派手な場所より、落ち着いた場所を好みます。不器用ですが、誠実に向き合える方と出会いたいです』
プラネタリウム。その単語に、私の指が止まった。自分と同じ趣味、そして「不器用」という言葉に、勝手な親近感を覚えた。私は深呼吸をして、自分から「いいね」を送り、メッセージを添えた。
「はじめまして。私もプラネタリウムが大好きです。一人でよく行くのですが、田中さんのおすすめの場所はありますか?」
それが、すべての始まりだった。
第3章:言葉の温度
田中さんからの返信は、その日の夜に届いた。
「美咲さん、はじめまして!プラネタリウムがお好きなんですね。嬉しいです。僕は〇〇にあるプラネタリウムの、リクライニングシートがお気に入りです。あそこは星の見せ方がとても丁寧なんですよ」
届いたメッセージは、他の誰よりも温かみがあった。何より、私の名前に触れ、私の好きなことに寄り添ってくれている。
それから、私たちの文通のようなやり取りが始まった。 田中さんは聞き上手で、私のたどたどしい言葉をいつも優しく受け止めてくれた。お互いの好きな星の話、仕事でのちょっとした失敗、子どもの頃の思い出。
「実は、僕はあまり女性と話すのが得意じゃないんです」
ある夜、彼が送ってきたメッセージに、私は驚いた。あんなに素敵な笑顔の写真で、仕事もバリバリこなしていそうな彼が?
「私もなんです。今までずっと、自分に自信が持てなくて……恋愛からも逃げてきました」
私は、これまで誰にも言えなかった本音を、画面越しになら打ち明けることができた。見ず知らずの人だから言えることもある。けれど、田中さんは、もう私にとって「見ず知らずの人」ではなくなっていた。
「美咲さんは、逃げてきたんじゃなくて、自分を大切にしてきたんだと思います。そんな美咲さんとお話しできて、僕は嬉しいです」
その言葉を読んだとき、視界がじんわりと滲んだ。30年間、ずっと自分を否定してきた私の心に、彼の言葉が優しく溶け込んでいった。
二週間が経った頃、彼から
「もしよければ、直接会ってお話ししませんか?」
という誘いがあった。 心臓が口から飛び出しそうなほど緊張したけれど、今の自分なら一歩踏み出せる気がした。いや、彼に会ってみたい。心からそう思った。
「はい、ぜひ。お会いできるのを楽しみにしています」
第4章:三〇年目の扉
デートの当日。私は予約していた美容室で髪を整え、何度も何度も鏡をチェックした。今日のために新調した、淡いラベンダー色のワンピース。
待ち合わせは、彼が教えてくれたプラネタリウムのあるビルの、入り口の柱の前。 遠くからでも分かるように、彼は紺色のジャケットを着ていると言っていた。
駅の改札を出てから、私の足取りは重かった。
「もし、写真と全然違うと思われたら?」
「話が弾まなかったらどうしよう」
ネガティブな思考が次々と湧いてくる。逃げ出したくなる気持ちを抑えて、私は約束の場所へと向かった。
柱の影に、一人の男性が立っていた。 背筋が伸びていて、少し緊張した様子で辺りを見渡している。写真で見た、あの田中さんだ。
「あ……田中、さん?」
声をかけると、彼はハッとした表情でこちらを向き、それからふわりと、あの写真と同じ、照れたような笑顔を見せた。
「……美咲さん。はじめまして。田中です」
「はじめまして、沢村美咲です。今日は、ありがとうございます」
お互いに頭を下げ合い、顔を見合わせた瞬間、それまでの不安が嘘のように消えていった。彼の瞳は、メッセージから伝わってきた通り、とても誠実で穏やかだった。
私たちは、まずプラネタリウムに入った。 暗闇の中、隣に並んで座る。手が届きそうな距離に、彼がいる。投影が始まると、満天の星々が頭上に広がった。
「綺麗ですね……」 「はい、本当に」
暗闇の中で交わした短い会話。でも、一人で見る星空とは、全く違う景色に見えた。隣に誰かがいる。その温もりだけで、世界がこんなにも優しく感じられるなんて。
上映後、私たちは近くのカフェに入った。 アプリの中ではあんなに饒舌だったのに、いざ対面すると、お互いに言葉を選んでしまって、沈黙が流れる。でも、それは気まずい沈黙ではなかった。
「……実は、すごく緊張してて。さっきからコーヒーの味が全然しないんです」
田中さんが困ったように笑いながら言うと、私もつられて笑ってしまった。
「私もです。心臓の音が自分でも聞こえるくらいで」
そこからは、堰を切ったように会話が溢れ出した。アプリで話したこと、まだ話していないこと。気がつけば、窓の外は夕焼けに染まっていた。
「美咲さん」 店を出て、駅へ向かう道すがら、彼が立ち止まった。
「今日は、勇気を出して会いに来てくれて、ありがとうございました。……僕、美咲さんと今日お会いして、もっと美咲さんのことを知りたくなりました。もしよければ、またデートに来てくれませんか?」
真っ直ぐな言葉だった。 30年間、誰からも言われたことのない、私が必要とされていると感じる言葉。 私は、心の底から溢れ出す喜びを噛み締めながら、彼の目を見て答えた。
「はい。私も、また田中さんに会いたいです」
第5章:重なり合う熱
それからの日々は、これまでの30年間が嘘のように色鮮やかに塗り替えられていった。二回目のデートは水族館、三回目は公園でのピクニック。私たちはゆっくりと、歩みを進めていった。
夜の公園で、彼から
「付き合ってください」
と告白されたとき、私は初めて差し出された彼の手を握り返した。30年間守り続けてきた心の殻が、音を立てて溶けていくのが分かった。
大人になってからの「初めて」は、どこか気恥ずかしく、それでいて何にも代えがたい輝きに満ちている。初めてのキスは、夜のドライブの帰り道だった。 心臓の音が激しく打ち鳴らされる中、触れるだけの、短くて優しいキス。唇が離れた瞬間、体温が一気に上昇するのが分かった。
「大切にするよ、本当に」
と、私の頭を何度も撫でてくれた彼の温もり。30歳の初キスは、魂が震えるような体験だった。
そして、季節が巡り、私たちは自然とその時を迎えた。 彼の部屋で二人きり、映画を観ていた夜のこと。彼の手が優しく私の髪に触れ、そのまま指先が頬をなぞる。
正直に言えば、怖さがなかったわけではない。「経験がない」という事実を彼がどう受け止めるか、上手く振る舞えないのではないか。けれど、彼が私の手を握り
「ゆっくりでいいから。美咲のペースに合わせるから」
と囁いてくれたとき、すべての強張りが消えていった。
触れ合う肌の温もり、重なり合う吐息。それはお互いの存在を丸ごと受け入れ合うような、神聖な儀式のようにも感じられた。初めて触れる異性の肌は想像以上に温かく、彼に身を委ねる中で、私は自分の体が自分だけのものではなく、誰かを愛するためにあるのだということを知った。
痛みや戸惑いよりも、彼に愛されているという絶対的な安心感が勝っていた。
「……大好きだよ、美咲」
彼の腕の中でその言葉を聞いたとき、私はようやく、30年間抱えてきた「自分は欠けている」という呪縛から解放された気がした。彼という存在を通して、私は自分のことをもっと好きになれる。そう確信した瞬間だった。
エピローグ:あの日の一歩が、私を連れてきた場所
あの日、アプリの登録ボタンを押した私。 画面を前にして、一人で泣きそうになっていた私。 勇気が出なくて、何度も諦めようとした私。
そのすべての過程、すべての迷いが、今この瞬間に繋がっている。 恋愛経験がないことを、私はずっと「欠落」だと思っていた。でも、田中さんは言ってくれた。
「真っさらな美咲さんと出会えて、僕は幸せだよ。これから一緒に、たくさんの『初めて』を作っていこう」
恋愛ストーリー。それは、ただ誰かと付き合うことだけを指すのではない。 それは、自分を嫌いだった私が、誰かを通して自分を認め、新しい自分へと生まれ変わる物語。
私のスマートフォンの画面には、今、田中さんからの「おやすみ、また明日ね。愛してる」というメッセージが光っている。 暗い部屋の中で、その光はとても明るく、そして温かい。
スマートフォンの向こう側に広がる世界は、私が想像していたよりもずっと広くて、優しかった。 そして私は、これからも一歩ずつ、新しい自分への軌跡を描き続けていく。 この、愛おしい世界の中で。