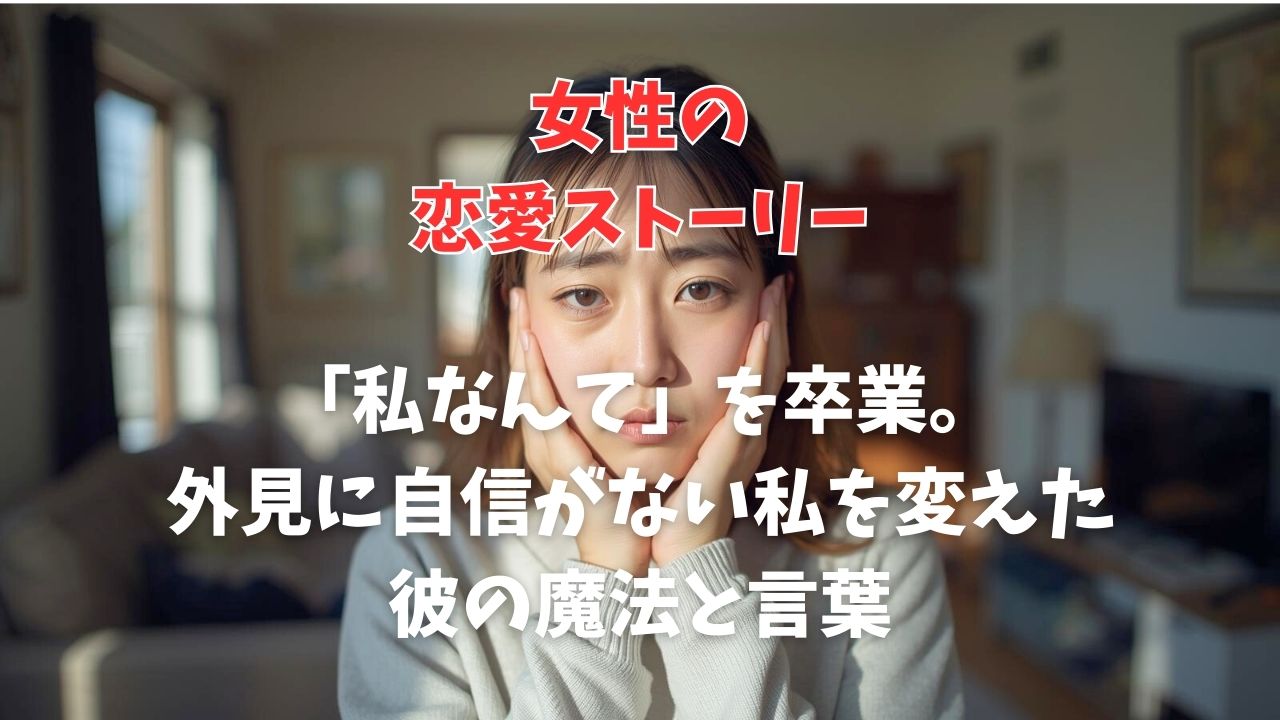「子ども」のころ、誰かに投げつけられた何気ない一言を、今も抱えて生きていませんか?
相手にとっては冗談半分の、明日には忘れてしまうような一言。けれど、感受性の強い子どもの心に刺さったその棘は、いつしか「私は美しくない」という呪いとなり、大人になっても鏡を見るたびに私たちを苦しめます。でも、その鏡に映っているのは、本当に「正解」のあなたなのでしょうか。
これは、外見へのトラウマから影のように生きてきた一人の女性が、マッチングアプリを通じて「ありのままの自分」を愛してくれる男性に出会うまでのストーリーです。自分ではコンプレックスだと思っていた部分を「魔法」のような言葉で肯定されたとき、20年間固く閉ざされていた心の氷が解け出す。本当の美しさとはどこにあるのか、その答えを見つけるための軌跡を辿ります。
プロローグ:消えない「言葉の棘」
「お前、本当にブスだよな」
放課後の教室で、心ない男子から投げつけられたその一言が、私の人生を決定づけた。 当時10歳の私にとって、それはただの言葉ではなく、一生脱げない「醜い仮面」を被せられたような衝撃だった。以来、私は鏡が嫌いになった。目立たないように、誰の記憶にも残らないように、影のように生きてきた。
事務職として働く奈緒(なお・仮名)、31歳。 周りの女性たちが楽しそうに新作コスメの話をしている時も、私は「私なんかが飾っても無駄だ」と心のシャッターを下ろしていた。子ども時代の小さな傷は、20年経っても消えない深い棘となって、私の自己肯定感を蝕み続けていた。
そんな私がマッチングアプリを始めたのは、病床の祖母が言った「奈緒の優しい笑顔が大好きだよ」という言葉を信じてみたくなったからだった。
第1章:加工アプリと偽りの自分
マッチングアプリの世界は、私にとって戦場だった。「顔写真必須」という文字を見るだけで動悸がする。ありのままの自分なんて、誰も見向きもしない。そう確信していた私は、スマートフォンの加工アプリで、肌を白くし、目を大きくし、自分でも誰だか分からない「偽りの自分」を作り上げた。
届く「いいね」の数が増えるほど、胸の奥がチリチリと痛んだ。
(これは私じゃない。みんな、この嘘の顔に騙されているだけ)
罪悪感に耐えきれなくなった私は、加工した写真をすべて削除した。代わりに、顔が半分隠れるような、大好きな図書館の片隅で撮った暗めの写真を一枚だけ載せた。これで誰もいなくなる。そう思っていた。
しかし翌日、たった一通のメッセージが届いた。
「素敵な雰囲気の写真ですね。奈緒さんは、どんな本を読んでいる時が一番幸せですか?」
それが、理学療法士として働く悟(さとる・仮名)さんとの出会いだった。
第2章:画面越しに透ける「心の色」
悟さんとのメッセージには、外見を褒める言葉は一度も出てこなかった。 代わりに、私たちが交わしたのは「心の内側」の話ばかりだった。
「子どもの頃、道端に咲いている名もなき花に名前をつけて遊んでいたんです」
私がふと漏らした幼い頃の思い出に、彼はこう返してくれた。
「奈緒さんは、目に見えない小さな輝きを見つけるのが上手な人なんですね」
自分の内面をこれほど丁寧に拾い上げられたのは、人生で初めてだった。画面越しに伝わる彼の温かな人柄に、私はいつしか「この人なら、本当の私を見せてもいいのかもしれない」という淡い期待を抱くようになった。
けれど、実際に会う約束をした日から、私の夜は再び恐怖に塗りつぶされた。
(会ったら、きっとガッカリされる。やっぱりブスだなって思われる)
第3章:震える手での「答え合わせ」
待ち合わせ当日。私は駅のトイレに30分も籠もっていた。 何度も鏡を見ては、ファンデーションで隠しきれないコンプレックスを数え、泣きそうになる。帰り道を探そうと一歩踏み出した時、メッセージが届いた。
『青いカーディガンの女性が奈緒さんですか? 遠くからでも、すごく優しい空気を纏っていて、すぐに分かりました』
逃げ道はなくなった。私は震える手でバッグを握りしめ、彼の前に立った。
「……はじめまして。写真と、違ってすみません」
うつむき、消え入るような声で謝る私に、悟さんは驚くほど穏やかな声で言った。
「奈緒さん。やっと会えましたね。……思った通り、とても綺麗な、春の陽だまりみたいな目をされている」
第4章:呪いが解ける瞬間
カフェでの会話が弾む中、私はどうしても聞かずにはいられなかった。
「悟さん。私は……美しくありません。子どもの頃に、はっきりとそう言われてから、自分の顔を直視できないんです」
隠し続けてきた20年間の呪いを吐き出した私に、彼はティーカップを置き、私の目をまっすぐに見つめてこう言った。
「奈緒さん。その子どもは、あなたの瞳の奥にある優しさを読み取る知性がなかっただけだよ。あなたが自分を嫌いな理由を100個挙げても、僕はあなたが愛おしい理由を1000個見つけられる」
彼は私の、コンプレックスだった厚い唇や、伏せがちな目を、一つずつ「宝物を見つけた子ども」のような純粋な瞳で褒めてくれた。
「この唇は、優しい言葉を紡ぐためにある。この目は、美しい景色を捉えるためにある。僕は、今の奈緒さんが誰よりも輝いて見えます」
第5章:魔法は、自分にかけるもの
彼との交際が始まってから、私の世界には色がつき始めた。 彼が「今日のリップ、春らしくて似合ってるよ」と言ってくれるから、少しだけ勇気を出して明るい色を買ってみる。彼が「奈緒の笑った顔が好きだ」と言ってくれるから、鏡の前で笑う練習をしてみる。
外見を変えるのは、最新のメイク術でも加工アプリでもなかった。「このままでいいんだ」という安心感と、誰かに愛されているという自信。それが、20年間固く閉ざしていた私の心の氷を、ゆっくりと溶かしていった。
ある日、公園で彼が私の写真を撮った。
「やめてよ、不意打ちは」
と笑う私に、彼は画面を見せてくれた。 そこに写っていたのは、加工なんて一切していない、シワを寄せて心から笑っている一人の女性の姿だった。
(……私、こんなに幸せそうに笑うんだ)
その時、私の中にいた10歳の少女が、ようやく救われた気がして涙が溢れた。
エピローグ:本当の「軌跡」
今の私のスマートフォンには、加工アプリは一つも入っていない。 代わりに、彼と一緒に食べたパンケーキや、ドライブで行った海、そして二人で並んで自撮りした、ありのままの笑顔が溢れている。
「私なんて」
という呪いを解いてくれたのは、一歩踏み出した自分の勇気と、その手を離さずにいてくれた彼の魔法のような言葉だった。
マッチングアプリ。それは、見た目の美しさを競う場所だと思っていた。 けれど、違った。それは、世界中の誰よりも自分の「心の色」を愛してくれるたった一人に出会うための、奇跡の入り口だったのだ。
夕暮れ時、彼の手を繋ぎながら私は思う。 20年前の私に伝えてあげたい。 大丈夫。そのままのあなたを「美しい」と言ってくれる人に、あなたは必ず出会えるから。