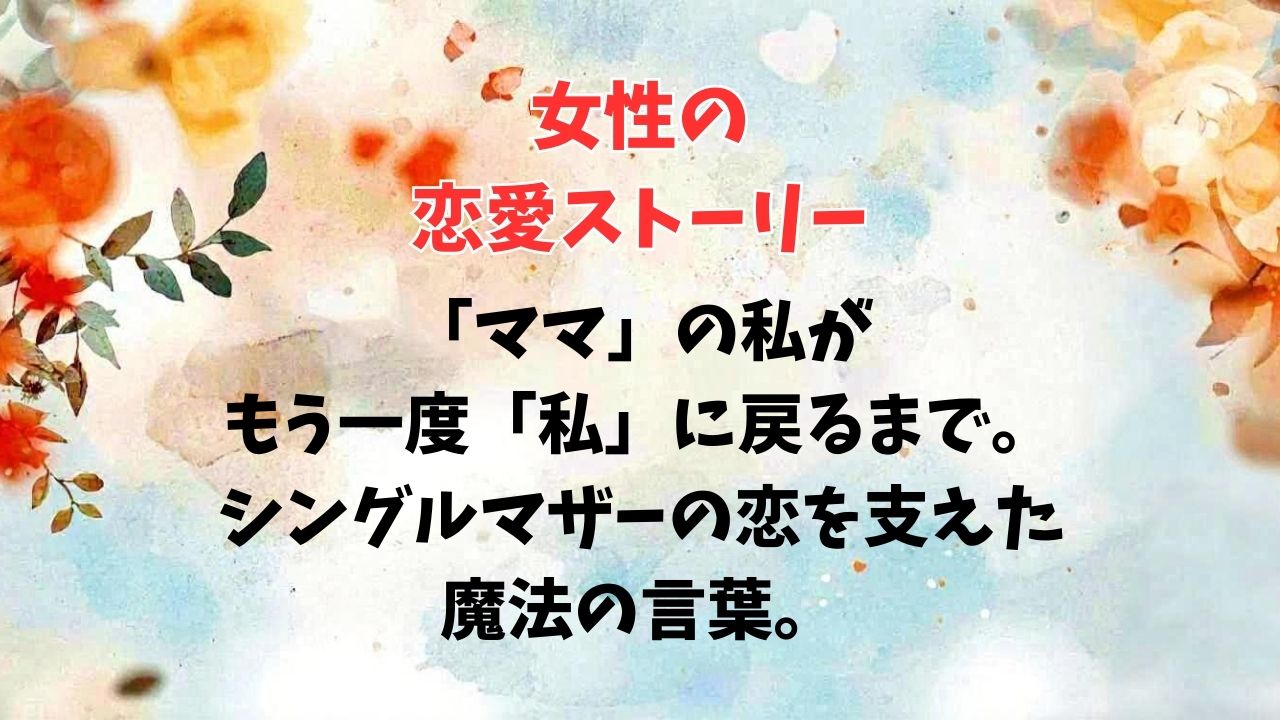これは、「母親」としての責任感と、「一人の女性」としての孤独の間で揺れていた女性が、新しい家族の形を見つけるまでのストーリーです。
32歳、シングルマザー。離婚の傷を抱え、息子のために自分の人生を封印してきた彼女。そんな彼女の頑なな心を溶かしたのは、マッチングアプリを通じて出会った、ある年上男性の深い包容力でした。
「母親が恋をするなんて」という罪悪感を乗り越え、愛する息子と共に、再び誰かを信じ、愛される喜びを取り戻していく。「ママ」の私が、もう一度「私」に帰るまでの温かな再生の軌跡を、ぜひご覧ください。
第1章:閉ざした「女」としての自分
「ママ、見て! お星さま!」
5歳になる息子・陽太(仮名)が、寝室の窓を指差してはしゃいでいる。
「本当だね、綺麗だね」
私はその小さな背中を優しく撫でながら、心の中で小さく溜息をついた。
私の名前は菜々子(仮名)、32歳。 離婚してから3年、女手一つで陽太を育ててきた。
毎日は戦場だ。朝は保育園への送り出しから始まり、時短勤務とはいえ責任のある事務の仕事、帰宅後は夕食、お風呂、寝かしつけ。
私の世界は、陽太という小さな太陽を中心に回っていた。
幸せだ。間違いなく、幸せ。 でも――。
陽太が寝静まった深夜2時。散らかったリビングで一人、冷めたハーブティーを飲んでいると、猛烈な「寂しさ」が襲ってくることがあった。
誰かと話したい。「ママ」としてではなく、「菜々子」として。
誰かに触れたい。誰かの体温を感じて、無防備に眠りたい。
「お前は母親に向いていない」
離婚の際、元夫に投げつけられた言葉が、呪いのように私を縛っていた。
恋愛なんて贅沢。別の男性を家庭に招き入れるなんて、息子に対して不謹慎だ。
そうやって、自分の心の渇きに蓋をして生きてきた。
ある日、ふと鏡に映った自分の顔を見て愕然とした。
疲れ果て、肌はくすみ、髪も適当に結んだだけの女性。そこには「母親」はいても、私がなりたかった「女性」はどこにもいなかった。
このまま、私は枯れていくのだろうか。
「ママ、笑って?」
陽太の言葉にハッとした。
私が満たされていなければ、この子を本当に幸せにすることはできないのではないか。
震える指先で、私は以前から気になっていたマッチングアプリをダウンロードした。
それは、母親であることを辞めるためではなく、母親であり続けるための、私の小さな反乱だった。
第2章:スマホの中の「母親ではない私」
アプリのプロフィール作成は、迷いの連続だった。
「シングルマザーであることを隠すべきか」
という問いが頭をよぎったが、私はあえて、一番最初にこう書いた。
『5歳の息子がいるシングルマザーです。平日の夜や週末は子どもとの時間を大切にしています。それでも、一歩ずつ将来を共に歩んでいける方と出会えたら嬉しいです』
案の定、届くメッセージの中には失礼なものもあった。けれど、その中に一つだけ、とても穏やかな文面があった。
「はじめまして、智也(仮名)といいます。お仕事と育児の両立、本当に尊敬します。僕も仕事中心の生活ですが、落ち着いた大人の関係を築ける方を探しています。無理のないペースでお話ししませんか?」
マッチングした彼は、42歳の建設コンサルタント。プロフィール写真は山登りの途中のもので、飾らない笑顔が印象的な人だった。
彼とのメッセージは、乾いた砂に水が染み込むように、私の心を満たしていった。
智也さんとのメッセージは、驚くほど心地よかった。
彼は私の「母親としての自分」を否定せず、かといって「母親」としてだけ見ることもなかった。
「陽太くん、今日は元気に保育園に行けましたか?」
「菜々子さん、今日もお疲れ様。夜は少し自分の時間を楽しんでくださいね」
彼からのメッセージが届くたび、スマホを握りしめる手が熱くなった。
誰かが私を気にかけてくれる。ただそれだけのことが、こんなにも嬉しいなんて。
そして何より、彼が私を「菜々子さん」と呼んでくれること。
その響きが、心の奥に錆びついていた「女としてのスイッチ」を、静かに押していった。
第3章:二人の時間、三人の未来
初めてのデートは、日曜日に母に陽太を預け、わずか2時間のランチだった。
待ち合わせ場所のカフェ。
現れた智也さんは、写真よりもずっと背が高く、落ち着いた大人の色気を漂わせていた。
「はじめまして、菜々子さん」
低くて優しい声。ふわりと香る、清潔なコロンの匂い。
目の前に座った彼と目が合った瞬間、心臓が痛いほど高鳴った。
久しぶりの、異性の視線。自分が「見られている」という感覚に、頬が熱くなるのが分かった。
「シングルマザーとの付き合いは、大変だと思いませんか?」
核心を突く質問を投げかけた私に、彼はコーヒーカップを置き、真っ直ぐに私の目を見て言った。
「大変かどうかは、二人が決めることですから」
彼は穏やかに微笑んだ。
「僕は、菜々子さんという一人の女性に惹かれたんです。そこに陽太くんという大切な存在がいるなら、それを含めてまるごと愛していきたい」
その言葉は、私の心のいちばん柔らかい場所に届いた。
ああ、私はこの人に頼ってもいいんだ。強がらなくていいんだ。
テーブルの下で、彼の手がそっと私の手に触れた。
その大きく温かい掌の感触に、私は久しぶりに「守られる」心地よさを思い出した。
第4章:高いハードル、初めての対面
それから数ヶ月、私たちは慎重に距離を縮めた。 智也さんは決して「早く会わせろ」とは言わなかった。
むしろ
「陽太くんの気持ちが一番大切だから、ゆっくり準備をしよう」
と私をリードしてくれた。
そして迎えた、公園での「初対面」。 智也さんは「ママの友達の智也おじさん」として、陽太の前に現れた。
「陽太くん、かっこいい靴履いてるね! 一緒にボール遊びしてもいいかな?」
年上の智也さんは、子どもとの接し方も驚くほど上手だった。陽太が転びそうになれば大きな手ですくい上げ、泥だらけになっても一緒に笑ってくれる。 走り回る二人の姿をベンチで見守りながら、私は不覚にも涙がこぼれそうになった。陽太に「お父さん」という存在が必要だと思ったことはなかったけれど、こうして二人で笑い合う姿は、私にとって何よりの救いだった。
夕暮れ時、陽太が智也さんの手をぎゅっと握ったとき、私たちの「新しい家族」の形が、うっすらと見えた気がした。
第5章:重なり合う夜、溶けていく罪悪感
陽太が彼に懐いた頃。 ある週末の夜、陽太が寝静まった後に彼が家に来てくれた。
リビングのソファ。隣に座る彼の体温が、シャツ越しに伝わってくる。
「菜々子さん、今まで一人で頑張りすぎたね」
彼が私の肩を抱き寄せ、髪を優しく撫でた。
その指先の優しさに、張り詰めていた糸がプツリと切れたように、涙が溢れ出した。
「これからは、僕に半分背負わせてほしい。菜々子さんと陽太くん、二人を僕の家族にしたい」
40代の彼の、落ち着いたプロポーズ。
私は涙でぐしゃぐしゃになった顔を、彼の胸に埋めて頷いた。
その夜、私たちは初めて深く結ばれた。
母親になってから、自分の体を「女性」として意識することは少なくなっていた。出産を経て変わった体型、妊娠線、日々の疲れが滲む肌。
明るい電気の下で見られるのが怖くて、私は思わず身を縮めた。
けれど、彼はそんな私の不安を見透かすように、私の体をまるで壊れ物を扱うように丁寧に愛してくれた。
「この体で、命を育んできたんだね。本当に綺麗だよ、菜々子」
耳元で囁かれる彼の熱い吐息と、愛おしそうな言葉。その一つ一つが、私の自信を取り戻させてくれる。
彼の腕の中で、私はただの「女」に戻っていった。
快楽だけではない。深い安心感と、全受容の喜び。
「愛されている」という確かな感覚が、体の芯から満ちていく。
彼に抱き締められながら、私は思った。
「私、幸せになっていいんだ」
母親だからといって、女性としての幸せを諦める必要なんてなかったのだ。
むしろ、私が満たされることで、陽太にももっと優しくなれる気がした。
エピローグ:新しい家族の軌跡。愛は増えていく。
今、休日のリビングには、三人の笑い声が響いている。
ステップファミリーとしての生活は、もちろん綺麗事ばかりではない。陽太が戸惑う日もあるし、ぶつかり合うこともある。
けれど、智也さんが隣にいてくれる。それだけで、私はどんな壁も乗り越えられる気がするのだ。
「ママ、智也パパと結婚してよかったね」
陽太がふいに言ったその言葉に、私は胸がいっぱいになった。
彼が来てくれてから、家の中にはいつも穏やかな空気が流れている。
私が笑顔でいることが増えたからだろうか、陽太も以前よりのびのびとしているように見える。
スマートフォンの待受画面は、三人で撮った写真。
そこには、かつての疲れ切った顔の私はもういない。愛する人と愛する子に囲まれ、柔らかく笑う「私」がいる。
もし、あなたが今、一人で孤独と戦っているなら。 どうか、自分の心の声に耳を塞がないでほしい。
「ママ」である前に、あなたは一人の魅力的な「女性」なのだから。
愛は、減るものではない。
分け合うほどに増えていき、あなたの世界を、そして子どもの世界をも温かく染めていく。
もう一度、誰かを信じてみる勇気は、きっとあなたの人生を鮮やかに彩ってくれるはずだから。